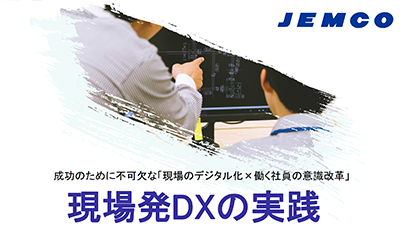生産の基本論~ものづくりの達人になるためにおさえるべきツボ~【第32回 仕掛品の移動】
文責:ジェムコ日本経営 コンサルタント 原 正俊
皆さんは、「IE」という言葉をご存じでしょうか?IEは、Industrial Engineering の略称で「生産工学」などと呼ばれ、「生産性向上」と「原価低減」を行うものです。「IE」の考え方に関する情報をコラムでお届けしてまいります。
32回目の今回は、「仕掛品の移動」についてです。
仕掛品の移動は作業設計の大きなテーマ
1つの工程で加工が終わったら、次の工程へ送る。これを最小単位で行うのが1個流しです。
このときの仕掛品をどのように移動させるかも、作業設計の大きなテーマです。
ここでは仕掛品の移動方法について3つご紹介します。
仕掛品の移動方法① 手送り
一つは、手で送る方法です。送っている時間は作業が中断することになるので、最短時間で送る方法を検討しなければならなりません。当然次の工程まで歩いていって置いてくるのは厳禁。身体は動かず手だけ伸ばせば送れるようにしなければなりません。次の工程がすぐ隣や前後に配置されているのが理想的です。前工程の作業者が置いた位置が後工程の作業者の取る位置になるように、工程配置とレイアウトを検討します。
仕掛品の移動方法② シュート
シュートは、重力を利用して仕掛品を送る方法で、段差が大きければ少し遠い位置まで送ることも可能です。勢いが強すぎて、仕掛品がシュートの壁に当ったりして傷つくのを防がなくてはなりません。このシュートは最小の仕掛りでなくても活用できますが、工夫しないと製品の停止位置をコントロールできないので、仕掛品が混ざったり、順番が変わると問題のある場合には要注意です。
仕掛品の移動方法③ 機械化
機械化は、ベルトコンベアーなどの機械を活用して送る方法です。離れた工程でも送ることができます。チャックや掴みなどの製品を固定する位置が決まっているものと、ただ単に置くだけのフリーなタイプがあります。単なる送りだけでなく、搬送装置で移動しながら製品を加工することができると作業者は送り行為をしなくてもいいので効率的になり、生産性も安定します。
工場のレイアウトを検討するときはこれらの製品や仕掛品の移動方法も忘れずに検討してください。