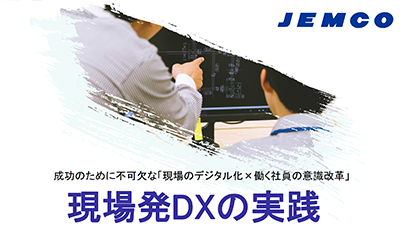生産の基本論~ものづくりの達人になるためにおさえるべきツボ~【第33回 中間仕掛品】
文責:ジェムコ日本経営 コンサルタント 原 正俊
皆さんは、「IE」という言葉をご存じでしょうか?IEは、Industrial Engineering の略称で「生産工学」などと呼ばれ、「生産性向上」と「原価低減」を行うものです。「IE」の考え方に関する情報をコラムでお届けしております。
33回目の今回は、「中間仕掛品」についてです。
仕掛け品が停滞することで生まれる弊害
工程の途中に仕掛品が停滞すると、様々な弊害を生じます。
例えば下記の3つのことのようなことです。
①停滞時間がそのまま工程の通過時間に加わってしまうので、材料投入から完成品になるまでの製造リードタイムが長期化する。
②仕掛品の置き方を工夫しないと、重なったり積み重ねられたりして下のものを出すために余計な時間を使います。あげくの果てには仕掛品を入れ替えたり、一時的に他所で移動したりする。全くのムダ行為。
③加工途中のある特定の製品を探すのに苦労する。重ねてあるものを一段一段確認したり、奥のものを探し出すのは大変な時間的ロス。
このほかにも停滞品の材料費が寝てしまうとか、紛失が発生するなどいいことはありません。
生産計画に問題のあるケースが多い
この発生原因はいくつかありますが、生産計画に問題のあるケースが多いです。製品特性にもよりますが、仕掛品の加工時間を計画できないと、“本日中に加工”というような粗い予定になってしまいます。
前工程が自分のところだけの予定を優先させてしまうと、停滞が生まれます。次の工程のことなどお構いなし。自分の工程の最適なスケジュールで加工した仕掛品を、どんどん次の工程へ送ってしまいます。次の工程は次の工程で予定があるので、送られたモノを次から次と加工できるわけではありません。
自分の予定に合わせて仕掛品を選んで加工すると、どうしても後回しになる仕掛品が出てくるわけで、それの積み重ねが大量の停滞品になってしまうのです。
防ぐための方法「引き取り方式」
これを防ぐのが、カンバンなどを活用した「引き取り方式」です。要求されたものしか送らないというルールを徹底すれば、前工程は勝手に加工すると自分のエリアに溜まってしまうので、必然的にブレーキがかかります。
検討が不足している工場が多い
使うときに必要なだけ次工程へ供給することは、理想ではあります。しかし、完全な実現は難しいものです。ライン化されていたり工程連結されていない限り、工程と工程が離れているのが当たり前なので、どうしても仕掛品は生まれます。それを最小にして、なおかつ欠品を起こさないための高度な管理が行われないと仕掛品に溢れた工場になってしまいかねません。
その検討が不足している工場が非常に多いのではないでしょうか。なりゆきでの生産になっている工場も時々見かけます。工場の特質、製品の特性、外注などの問題要因、これらを考慮した最適な生産管理体制の構築は、どの工場でも課題のようです。