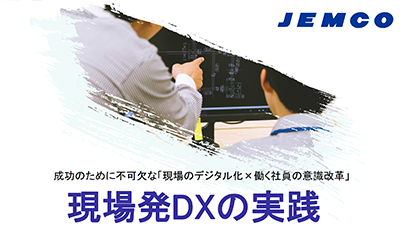生産の基本論~ものづくりの達人になるためにおさえるべきツボ~【第21回 設備の清掃】
文責:ジェムコ日本経営 コンサルタント 原 正俊
皆さんは、「IE」という言葉をご存じでしょうか?IEは、Industrial Engineering の略称で「生産工学」などと呼ばれ、「生産性向上」と「原価低減」を行うものです。「IE」の考え方に関する情報をコラムでお届けしております。
21回目の今回は、「設備の清掃」についてです。
目次
設備の能力発揮のために必要な清掃
設備は、きちんと整備され、清掃されていればその能力を長いあいだ発揮してくれます。計画的にかつ継続的に清掃しましょう。
清掃には下記の5つの種類があります。
清掃の種類① 日常清掃
日常的に行う清掃。毎日、たとえば就業後に自分の作業場所のまわりの掃き掃除や、設備の主要部分について切り粉を落としたりする基礎的な清掃です。
清掃の種類② 定期清掃
週・月・年単位で決められたときに行う清掃。日常清掃ではなかなか掃除しにくい、奥や細かい部分を清掃します。
清掃の種類③ 点検清掃
清掃と合わせて、設備の点検を行います。調整を兼ねて行うこともあります。必要あれば、部品の定期交換や不具合の補修も行います。
清掃の種類④ 集中清掃
設備のこびりついたような汚れの除去を中心に、設備を止めて行う清掃です。時間をかけて徹底的な清掃を行います。職場の中では、設備や備品をどかして行う清掃となります。
清掃の種類⑤ オーバーホール
設備を分解して洗浄する清掃です。当然部品の交換も伴います。不具合箇所は分解修理し、再度組み立てて調整を行いトラブルを解消するので、保全清掃ともいいます。
清掃の意味を理解して清掃計画を立てる
これらの清掃の意味を理解して、清掃計画を立てましょう。それと同時に、チェックシートなどで決められたとおりに清掃が行われているかを把握できるようにします。そして、清掃の記録を残しておくことが肝要です。清掃の実施状況とトラブルの発生状況との対比から清掃計画を修正していきます。清掃点検したところはトラブルを起こしてはなりません。