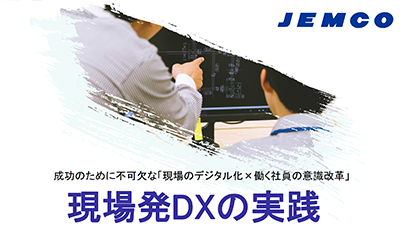生産の基本論~ものづくりの達人になるためにおさえるべきツボ~【第23回 設備のトラブル対応】
文責:ジェムコ日本経営 コンサルタント 原 正俊
皆さんは、「IE」という言葉をご存じでしょうか?IEは、Industrial Engineering の略称で「生産工学」などと呼ばれ、「生産性向上」と「原価低減」を行うものです。これからこの「IE」の考え方に関する情報をコラムでお届けしてまいります。
23回目の今回は、「設備のトラブル対応」についてです。
故障の影響を減らすために必要な2つのこと
設備は故障を起こすものです。では、その影響を最小限にするためにはどうすべきでしょうか。
それには、下記の2つが必要です。
●故障の対応を迅速に行うこと
●故障原因を除去して故障そのものを起こさせないようにすること
設備のトラブルが発生したときどうする?
設備のトラブルを起こさないように、維持管理を行い、点検します。しかし、それでもどうしてもトラブルは発生します。
設備のトラブルが発生したとき、そこにいる作業者が対応できれば、トラブルの影響は最小限に留まります。ところが、設備トラブルに完全に対応できるほどのスキルを持つ作業者は少ないし、なかなか育っていきません。そうすると保全に修理をお任せということになります。
トラブル対応の問題点
海外工場ではそのようなことが多いのですが、ある程度の簡単なトラブルは、作業者でも対応できるようにしなければなりません。何でもお任せでは停止する時間が長くなってしまいます。
問題は、なまじトラブル対応の経験があるばかりに、作業者が自分で何とかしようとして時間をかけることです。何十分も、時には何時間もかけて修理しようとしてうまくいかず、結局保全を呼ぶことになったら、この作業者の対応時間は何の意味もありません。
トラブル対応の3つのポイント
大切なのは下記の3点です。
●作業者でも対応できるトラブルを明確にすること
●トラブル対応あるいは原因追求の時間のリミットを決めること
●修理できないまでも原因が把握できるように作業者を教育すること
10分とか15分と言うように時間を決めて、「それ以上かかると判断したら保全を呼ぶ」あるいは「原因だけ突き止めて保全を呼ぶ」というルールを決めることが重要です。そうすることで設備の停止時間を短縮することができるはずです。
作業者と保全者の役割を明確にして、ルールを作るようにしましょう。